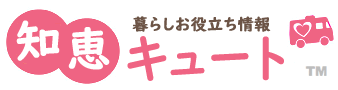誰しも、「めんどくさい」と感じることがあるものですね。
私はかなりのめんどくさがり屋です。
あなたは「めんどくさい」と感じたとき、どうしていますか?
今回は、なぜ「めんどくさい」と感じるのか、そして「めんどくさい」をスッキリ手放す方法をお伝えします。
また、少し立ち止まってみると、「めんどくさい」を通して学べることも見えてくるかもしれません。
この記事を読むのもめんどくさいという方は、ぜひだまされたと思って5分間だけ読んでみてくださいね。
「めんどくさい」と感じるのはどんなとき?
「めんどくさい(面倒臭い・めんどうくさい)」の意味は、「手間や困難さを考えて気が進まない。面倒である。おっくう。わずらわしい」など。
あなたは、どんなときに「めんどくさい」と感じますか?
日々の生活の中で「めんどくさいな」と感じられる場面の例をあげてみましょう。
- 朝起きて歯を磨くのがめんどくさい
- お弁当の用意がめんどくさい
- 仕事に行くのがめんどくさい
- 部屋をそうじするのがめんどくさい
- 健康やダイエットのために食事を考えたり、運動をするのがめんどくさい など
- 人と会うこと自体がめんどくさい
- 苦手な人や自分と価値観が合わない人との関わりがめんどくさい
- 恋愛するのがめんどくさい など
きっと、この他にもさまざまな「めんどくさい」があることでしょう(私はたくさんあります)。
もう読むのがめんどくさい、という方は読みとばしても大丈夫です。
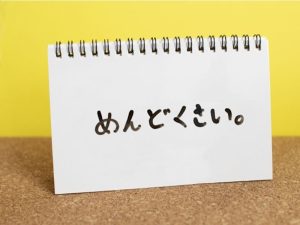
なぜ「めんどくさい」と感じるの?5つの理由
「めんどくさい」と感じる理由は人それぞれかもしれませんが、考えられる原因をあげてみましょう。
身体的な要因
- 脳の酸素不足、活性化不足
- 睡眠不足
- 疲れている
脳の酸素が不足していたり、睡眠不足、心身の疲労など身体的な要因でめんどくさいと感じることも多いのです。
「めんどくさい」は、ささいなものでも、積み重なったり抱え込んでしまったりすると、体にも影響を与えます。
あまりにもだるい、疲労感が強い、無気力でなにもかもがめんどくさい、といった状態が2週間以上続いているようであれば、医療機関に相談することがすすめられます。

取りかかるのがめんどくさい
- やるべきことがたくさんありすぎる
- 同時にいくつものことをやろうとしている
- 最初から完璧を目指す、よい結果を求めすぎる、期待しすぎる
同時にあれもこれもと進めようとしても、かえって効率が悪く、結局どれも中途半端になってしまうことがあります。
自分ひとりで処理できることには限界がありますよね。
ときには他の人の力を借りながら進めることも大切です。
また、真面目すぎる人や完璧主義の人は、うまくやらなければと考えすぎてしまう傾向が。
やることのハードルを上げすぎると、取りかかること自体がめんどくさくなってしまうかもしれません。
ハードルを下げ、できることからひとつずつやってみることが大切ですね。
感じ方やとらえ方
- やらされている感がある(主体性がない)
- やらなくてはと頭ではわかっているが、行動できない(行動したくない)
- 行動しなくてもなんとかなると思っている
- うまくいかないと自分やまわりを責めるクセがある
人から強制されたり、自分が納得して取り組めない場合、消極的になる傾向があります。
また、うまくいかないときに自分やまわりを責める傾向のある人も、「どうせまたうまくいかない」と考えてしまいがちです。
自分はどうありたいのかを考えてみるよい機会になるかもしれません。

怖い、逃げたい、不安
- 不安な気持ちになったり、傷つくのが怖い
- 新しいことにチャレンジすることや、変化することが怖い
- 失敗するのが怖い
- 苦手なこと、不得意なことだから
- やらない理由やできない理由ばかりを考える
人間を含めた生物には、環境の変化にかかわらず体内環境を一定に保つ「ホメオスタシス」という調整機能が備わっています。
人間は健康を保つため、本能的に変化を嫌うようにできているのです。
しかし、人間は変化を嫌うといっても、「慣れる」こともできる生物。
同じことを何度も繰り返して慣れてしまえば、めんどくさいと思わなくなり、当たり前にできるようになります。
つまり、めんどくさいと感じていたことも習慣にすることができるのです。
また、苦手なことや不得意なことへのチャレンジは、うまくいかなかったらどうしよう、などと考え、めんどくさくなることも多いもの。
考えすぎて一歩踏み出せないときには、「どうしたらできるか」に目を向けていくことが必要かもしれませんね。
ただ、不安な気持ちや怖いという感情を抱くことは、悪いことではありません。
自分を守るために必要な気持ちや感情だと考えられるからです。
うまくいかないときには、ありのままの事実を受け入れ、別の方法を試してみることも必要ですね。
自分の心や体と相談しながら、失敗を恐れずに試行錯誤していきましょう。

人間関係がめんどくさい
- コミュニケーションが苦手
- ありのままの自分を出せずに、対人関係でストレスを抱えている
- 価値観の違う相手に無理して合わせようとしている
- がんばっても認めてもらえない
対人関係は、思い通りにいかないことも多いもの。
あまりにも自分の思い通りにしたいと願ったり、人に期待しすぎたりすると、ストレスを感じます。
また、言いたいことがうまく伝えられない、自分の主張を受け入れてもらえない、無理して自分を抑え込むことも、つらいですよね。
対人関係に大きなストレスを抱えていたり、コミュニケーションに苦手意識があると、人と関わること自体がめんどくさくなるかもしれません。
ありのままの自分を認め、そのままで大丈夫だという自己肯定感を高めていくことも大切ですね。

あてはまるものが多くても、罪悪感を抱いたり、決して自分を責めたりしないでくださいね。
めんどくさいのは、悪いことではありません。
「めんどくさい」を解消するために、もっと合理的な方法を見つけたり、商品やサービスが生まれたりすることもありますよね。
ときには自分を守るために必要な場合もあるでしょう。
もしかしたら、心や体からの大事なメッセージかもしれません。
「めんどくさい」を手放すには、まずはめんどくさいと感じている自分を「受け入れる」ことが大切です。
「めんどくさい」を手放すコツは?
では、どうしたら「めんどくさい」という気持ちを手放せるのでしょうか?
いくつか対処方法をあげてみましょう。
5秒でできる方法もありますよ。
めんどくさくてもぜひトライして、自分に合った方法を見つけてみてくださいね。
- 5秒ルールで始める
「5秒ルール」とは、アメリカの弁護士・テレビ司会者のメル・ロビンス氏が提唱している方法で、やり方は簡単です。
「5,4,3,2,1,GO!」と言うだけ。
やらなくてはいけない大切なことがあるのに、めんどくさくなって取りかかれない、行動を起こせないときに効果があります。
最初は、朝起きる、歯を磨くなど簡単なことから始めてみましょう。
慣れてきたら、家事や仕事に取りかかるときにやってみると、スムーズに始められるようになります。
やろうと思ってから5秒以上経過すると、脳はやらない理由を考え始めるとのこと。
つまり、めんどくさいと思う前に動こう、ということですね。

- 5分間だけやってみる
めんどくさくて先送りしている物事を、試しに5分間だけと決めてやってみます。
5分間できたら次は10分間・・・・・・と、少しずつ時間をのばしていきましょう。
最初は1分間だけ、3分間だけでもOKです。
これを続けていくことで、抵抗なく取りかかることができ、習慣化することができます。
たとえば、部屋のそうじ・片付けなどからやってみるのはいかがでしょうか。
少しでもできた自分を認めて自信につなげていきましょう。 - ほんの少しだけ手を付ける
やるべきことの始めだけ手を付けておきます。
めんどくさくてやる気になれなくても、ちょっとした作業に手を付けておくと、その後スムーズに始めることができるのです。
たとえば、使ったお皿を流しに持っていって水に漬けておく、PCを立ち上げて使用するソフトを開いておく、など。
また、次の日にやるべき仕事の一部だけ前日に手を付けておくと、翌日スムーズに取りかかれます。
やる気が出るのを待つよりも、ほんのちょっとだけ行動したほうが早いのです。

- 作業興奮を利用する
「作業興奮」とは、作業を始めると脳の「側坐核(そくざかく)」という部位が活性化し、やる気が出てくるという作用のことです。
手や足、頭を使うことで、脳の「側坐核」が刺激され、「ドーパミン」という意欲や快感をつかさどる脳内伝達物質が分泌されます。
そのドーパミンの分泌によって、やる気が出てきて作業を続けられる、というしくみです。
前述の5分間だけやってみる方法や、始めだけ手を付ける方法もこのしくみを利用しています。
側坐核は作業を始めてから5分~10分ほどで活性化するので、とにかく少しでもやり始めることが必要なのです。
たとえば、年末の大そうじや部屋の模様替えなど、めんどくさいけど一度手を付けてしまえば一気にできた、という経験はありませんか?
まず、5秒ルールや5分間だけやってみる方法で簡単なことから取りかかりましょう。
そして、作業興奮が起きて調子が乗ってきたら、難しいことや苦手なことに取り組む、という方法がおすすめです。

- ベイビーステップで始める
あまりに目標を高く設定したり、最初から完璧を目指したり、すぐによい結果を求めたりすると、取りかかるのがめんどくさくなりませんか?
そんなときは、「ベイビーステップ」で、始めてみましょう。ベイビーステップとは?
ベイビーステップとは、赤ちゃんのよちよち歩きのような、小さな一歩のこと。
「スモールステップ」ともいわれ、どんなに小さくてもとにかく一歩踏み出す、という方法です。ベイビーステップの進め方
★目標を分ける
目標を達成するためにやることを、細かく分けて書き出していきます。
このとき、「今すぐにできる行動」まで小さく分けて、ハードルを低く設定するのがポイントです。
★やってみる
できそうなことからすぐ実行し、達成したら少しずつハードルを上げていきましょう。
たとえば、健康を維持する目的で1日7,000歩以上歩くぞ!という目標を立てたとします。
今まで本格的にウォーキングをしたことがないのなら、ウォーキングシューズやウェアを買いに行くことから始めてもよいでしょう。
そして、とりあえずウォーキングシューズを履いてみる、近所のお気に入りの場所を散歩する、それができたら1日5,000歩にチャレンジするなど、少しずつハードルを上げていきます。
今すぐできる簡単なことや、ちょっとだけがんばればできそうなことでよいのです。
また、最初から完璧を求めないこと、すぐによい結果を求めないことも大事ですね。
たとえ今日できなかったとしても、明日からまたがんばればよいのです。
★ゴールは柔軟に
結果を積み上げていった先のゴールは柔軟に。
多少思っていた結果と違っていても、やりたいことがだいたい達成できていたらOKとしましょう。
★ベイビーステップを繰り返す
前述した「5秒ルール」や、「5分間だけやってみる」方法、「ほんの少し手をつける」方法で、小さな一歩を踏み出すのも効果的です。
さらに、一歩踏み出してしまえば「作業興奮を利用する」ことにもつながります。
小さな目標を達成していくことで自信が持てるようになり、モチベーションも上がるでしょう。
★ごほうびを用意する
目標を達成したら自分で自分をほめることも大切です。
ポイントカードを作り、ひとつ目標を達成するごとにポイントがたまってごほうびをゲットできる、というしくみにしてもよいですね。
このとき、ごほうびを得たその先の楽しみをイメージするとよいでしょう。
たとえば、ごほうびとしてケーキを買うとします。
ひとりでゆっくり食べるのもよし、家族や友人とシェアして楽しい時間を過ごすのもよし、一歩先にある楽しみを思い描いてわくわくしてみましょう。
めんどくさくてもがんばれそうな気がしてきませんか?

- 30秒間体に意識を集中する
脳は、考える余裕のあるときに「めんどくさい」と感じるようです。
そこで、30秒間だけ体に意識を向けてみてください。
「『めんどくさい』がなくなる脳」の著者で、脳内科医・医学博士の加藤俊徳氏による方法をご紹介します。
目をつぶって片足立ちになり、30秒間声を出して数えるというものです。
やり方は簡単ですが、やってみると意外にバランスをとるのが大変。
でも、その間は「めんどくさい」と考える余裕はなく、やったあとはなぜか頭がスッキリします。
これは、脳のいろいろな部位を同時に使うので、脳を一気に活性化することができるとのこと。
また、脳研究者の池谷裕二氏は、簡単でユニークな方法をすすめています。
目をつぶって頭の上にテニスボールをのせ、30秒間バランスをとるというものです。
このとき、頭の上にテニスボールがのっていることに意識を集中させます。
こちらも同様に、やったあとは頭がスッキリし、目の前のことに集中できるようになりました。
めんどくさいと感じたときには、気分転換をして脳の違う部位を使うようにするとよいのですね。
特に新しいことにチャレンジするためには、今まで使っていない脳細胞により多くの酸素を送って活性化させる必要があります。
体に意識を集中させることは、気軽にできて効果があるので、おすすめです。

- ルーチンワークの順序を変えてみる
私は朝が苦手ですが、実は脳も朝が苦手らしいのです。
朝は脳がまだ覚醒しておらず、酸素の供給もうまくいっていない状態。
たとえば、朝起きて歯を磨くのがめんどくさいと感じる人は多いのではないでしょうか。
歯磨きのように、手や指先を使う細かい動作のことを「巧緻(こうち)動作」といいます。
この巧緻動作は脳に負担がかかるので、まだ起きていない脳で行うのはめんどくさいと感じるのです。
そういうときは、ストレッチや、ラジオ体操、軽い散歩などの体を大きく動かす「粗大(そだい)運動」を行うと、脳への負担が少なくて済みます。
つまり、いつもと順序を変えて、朝起きて歯を磨く前にストレッチなどを行い、脳を少しずつ目覚めさせるとよいのです。
めんどくさいことは、こうした脳のしくみも考えて取り組むとよいかもしれませんね。

- やらないことリストを作る
やることリスト(To Do リスト)を作ってやるべきことを整理しているうちに、めんどくさくなることはありませんか?
やるべきことが多すぎて優先順位がつけられず、同時にいくつものことをやろうとしたが結局達成できなかった、ということもあるかもしれません。
そんなときにおすすめしたいのが、「やらないことリスト(Not To Do リスト)」を作ること。
「足し算」ではなく「引き算」をしてみるのです。
やらないことリストを作ることによって、時間や労力を効率的に使うことができ、今の自分にほんとうに必要なことに集中できるようになります。
「今やる必要はない」「やらなくてもなんとかなる」「やりたくない」「やめたい」、そして「めんどくさい」など、どんなささいなことでもよいので、書き出してみましょう。
そして、オセロをひっくり返すように「やりたいこと」「自分にとって必要なこと」「やってもよいこと」「ほんとうはどうしたいのか」に変換してみましょう。
たとえば・・・・・・- ダイレクトメールのチェック→必要のないメールは配信解除する
- 毎日掃除機をかける→毎日ではなく週3回にする
- 毎日の食事作り→たまにはテイクアウトや半調理済みの食材セットを利用する
- 合わない人とのお付き合い→気が進まないときは誘いを断る
- 愚痴や不満を言う→ものごとのよい面を探す、なにごとにも感謝する
- 人の悪口を言う→人のよいところを探す、ほめる
「やらないことリスト」を裏返してみると、ほんとうに「やりたいこと」や「必要なこと」、「本音」が見えてきます。
自分の気持ちがはっきりしてやることがシンプルになれば、気持ちも軽くなり、前向きに取り組めるようになるでしょう。 - 人間関係のストレスを減らす
人間関係がめんどくさいと感じている人も多いかもしれませんね。
人間関係のストレスを軽減するためのヒントを3つあげてみます。適度な距離を保つ人間関係のストレスを減らすためには、お互いにとってちょうどよい距離を保つことも必要。
特に、苦手な人や自分と合わないと感じる人とは、自分を守るためにも距離をとってよいのです。
SNSによる人付き合いに疲れたら、時間を決めてSNSから離れ、ゆっくり過ごしてみるのもおすすめ(慣れると意外と平気なものです)。
チェックするのは1日3回、10分間など、マイルールを設定して適度に付き合っていくのもよいですね。2:7:1の法則人からどう思われるか気にしすぎてしまう人は、心理学者のカール・ロジャーズによる「2:7:1の法則」で考えるとよいでしょう。
「2:7:1の法則」とは、自分のまわりにいる人に対する考え方です。自分のまわりにいる10人のうち、2人はとても気が合う人。味方。
1人はとても気が合わない人。敵。
残りの7人はどちらでもない人。自分と気が合い、味方になってくれる2人を見極めることが大事です。
そして、その他の人たちから何を言われても気にしないこと。
これが人間関係のストレスを減らすコツのひとつです。『さ・し・す・せ・そ』の法則コミュニケーションを円滑にし、ストレスを軽減するには、聞き上手になることもおすすめ。
相手を認める言葉を意識しながら、相手の話に興味を持って聞いてみましょう。
「『さ・し・す・せ・そ』の法則」が、役に立ちます。「さ」さすがですね!
「し」知りませんでした!
「す」すごいですね!
「せ」センスがありますね!
「そ」そうなんですね!
- 心と体を休め、生活を整える
なにもかもがめんどくさいときは、心や体がSOSを出しているのかもしれません。
心と体をしっかりと休め、基本的な生活を整えることが必要です。
「めんどくさい」は心だけでなく、体を整えることで解決することがあります。
心を元気にするために、まず体から整えてみましょう。
特に、食事と睡眠は重要です。
たとえば、食生活が乱れ、栄養が不足していれば、体のコンディションは悪化します。
体のコンディションが悪ければ、心も元気がなくなって「めんどくさい」と感じてしまうのは無理もありません。
そんなときは、食生活を改善してみましょう。食生活を改善するためのヒント
肉類や魚類、豆腐、卵などのタンパク質はしっかりとる。1日に手のひら3~4つ分程度。
朝食や昼食で炭水化物を控えすぎずにしっかりとる。糖質、脂質は控えめに。
野菜(特に緑黄色野菜)、果物はしっかりとる。タンパク質と同量、同時にとるとよい。
コーヒーや緑茶などカフェインを含む飲み物は1日3杯程度にとどめる。アルコールや甘いものは控えめに。そして、睡眠が足りずしっかり休息がとれていないと、疲れやストレスがたまって「めんどくさい」と感じやすくなります。
逆に、よく眠れたときは心も元気になり、やる気になれるのではないでしょうか。
毎日よい睡眠をとり、心と体をしっかり充電したいものですね。よい睡眠をとるためのヒント
起きたら太陽の光を浴びる(朝日が浴びられる時間に起きる)。朝日を浴びることで生体リズムを整える。
昼寝は午後4時までに1時間以内。夜の睡眠に影響が出ないように。
寝る2時間前はリラックス。スマホは見ない、音楽を聴く、ハーブティーを飲む、ぬるめの温度で入浴するなど。
睡眠時間は連続して最低6時間確保する。
寝る直前のアルコールは避ける(睡眠が浅くなる、途中で目が覚める)。
日中は体を動かす。また、脳に酸素が行き届いていなければ脳も十分な働きができません。
深呼吸を心がけましょう。
ストレスを抱え込まないことも大切です。
軽い運動をする、思い切って休む、気分転換をする、リフレッシュする、楽しいことや好きなことに集中する、などを積極的に行うとよいでしょう。
「めんどくさい」が教えてくれること
やっかいな「めんどくさい」ですが、そこから学べることもあるのではないでしょうか。
例をあげてみましょう。
- めんどくさいのは心や体からのサイン
どうしても嫌なことはがまんしなくてもよいのです。
がまんし続けて体調を崩してしまえば、元も子もありません。
自分を守ることも必要です。
心の声に耳を傾けて、自分の意志で行動してみましょう。 - 人生は行動あるのみ
「めんどくさい」と感じたときは、苦手なことにチャレンジする、また得意なことを見つけるチャンス。
自分を成長させるチャンスなのです。
心と体を整え、失敗を恐れずにとにかく小さな行動を起こしてみましょう。 - 他の人と比べるのをやめる
難しいことかもしれませんが、他の人と比べるのをやめてみましょう。
そして、めんどくさいと感じている自分のことを責めずに受け入れ、許すことにチャレンジしましょう。
すべてを完璧にやる必要はないと開き直ることも必要です。
自分はどうありたいか?を考え、整理してみるのもよいでしょう。
紙に自分のめんどくさいと思うことや正直な気持ちを書き出してみるのもおすすめです。
人それぞれ「めんどくさい」の感じ方や考え方は違います。
自分なりに感じたことや学んだことを大切に生かしていきましょう。

まとめ
「めんどくさい」と感じる原因や、スッキリ手放す方法についてお伝えしました。
めんどくさい理由はさまざまですが、自分を責めず、考えすぎず、とりあえずちょっとだけ動いてみましょう。
また、めんどくさいという気持ちは意外と奥が深く、いろいろな要素や対処法があることもわかりました。
めんどくさいことから学べることもたくさんあります。
これを機に物事に対する姿勢を見直したり、自分はどうありたいのかを考えるきっかけになるとよいですね。
自分なりの「めんどくさい」との付き合い方を探していきましょう。
そして、めんどくさいと感じながらもこの記事を読めた自分のことを、ほめてあげてくださいね。